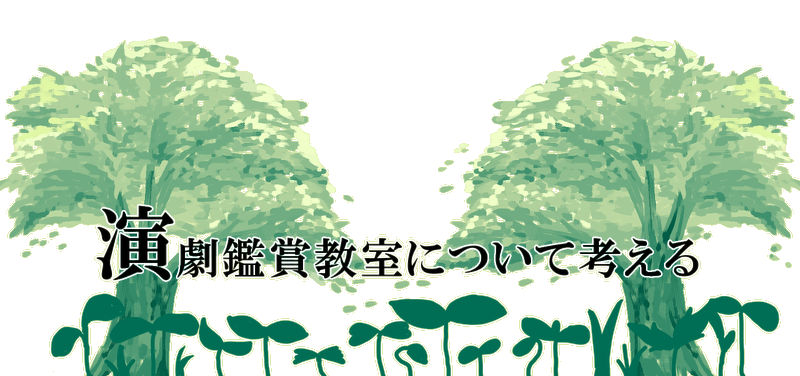
第二回
「学校公演の灯を消すわけにはいかない」
津曲学園鹿児島高等学校教諭
鹿児島県高校演劇常任理事 谷崎 淳子
「学校公演の灯を消すわけにはいかない」
津曲学園鹿児島高等学校教諭
鹿児島県高校演劇常任理事 谷崎 淳子
舞台作品のDVDというものに、最近までまったく関心がなかった。舞台はナマで見るもの、という思いがあり、 劇場中継のテレビ番組もほとんど見たことがなかった。ところがこの春、視聴覚の鑑賞用DVDの中に映画だけでなく舞台作品も加わったのをきっかけに、 演劇部の生徒と一緒にいくつかの作品を見た。おもしろかった。劇場内の緊張感が十分に伝わってきた。不思議なのはDVDで見られたのだからわざわざ劇場に行かなくてもよい、 という気持ちは全く湧いてこず、逆にこの作品をぜひ劇場で見てみたい、と思ったことだった。ナマの舞台を思う存分見たい、という気持ちが久々に募った。
芝居好きということでは人後に落ちないと思っている私でも、実際に観劇する機会はひじょうに限られている。熱心な演劇ファンは東京や大阪とまで行かなくてもせめて福岡の劇場までまめに足を運ぶようだが、 そこまでの積極性はない。というか、仕事をやりくりしてまで行く気力も体力もない。いきおい、劇団の地方公演を待つことになるのだが、地方の悲しさ、せっかく楽しみにしていた作品がやってきても、 そのワンチャンスに仕事の都合がつかなければ見ることはできない。観劇のチャンスが少ない、ということが、地方における演劇ファンをどれだけ失うことになっているか計り知れない。 まして、社会に出る前に見る機会がなかったら、演劇を好きになるチャンスさえない、ということになってしまう。
そこで、演劇鑑賞教室である。
演劇は、特に地方巡演は究極のアナログだと私は思っている。この便利な時代に、行った先のホールや学校の体育館で、いちいち大道具を立ててはバラし、バラしては立てて…。 そして映像にすれば何回でも再生できるのに、行った先で演技を繰り返す。効率だけを考えれば、まったく理にかなわない。
そのアナログの部分を、子どもたちに観せたい。世の中がどんどん軽便なものだけを求めていく中で、人の力だけで、学校の体育館が別世界になるところを見せたい。 CG全盛の時代に、生身の人間が目の前で壮大な宇宙を表現するところを見せたい。カリキュラムの関係で、学校における演劇鑑賞がどんどんカットされる状況にあるという。 大切なものは何かと考えれば、カットするものは違ってくるはずなのに、と思う。私の学校は今のところ、3年サイクルで、演劇、音楽、講演という特別行事のローテーションをきっちり守っている。 毎年、それぞれの行事の意義は高く評価されている。ただ今後、私立には少子化による経費の面の問題が出てくる。学校行事の見直しが課題になることは十分考えられる。
もうずいぶん前のことになるが、忘れられないことがある…。 「先生、あの劇って、うちの学校がモデルなんですか……」『翼をください』の学校公演が終った後、一人の生徒が私に質問した。 彼は真顔だった。確かに、私の学校は『翼をください』の花房学園とよく似ている。入学生のほとんどが公立高校の受験に失敗していること。 学校の目と鼻の先に、県内随一の進学校である県立高校があること。しかしそんな私立高校は日本中いたる所にいくらでもあるだろう。 そんなことはちょっと考えればわかりそうなものだが、私は「そんなワケないじゃない」と笑い飛ばすことができなかった。 作品の持つ普遍性に、若い感受性が強烈に反応したのだと思った。それをこそ、感動、と呼ぶのではないのか。映画やTVドラマではこうはいかないだろう。 生身の人間によって目の前で展開された物語だからこそ、生まれた感動なのだろう。
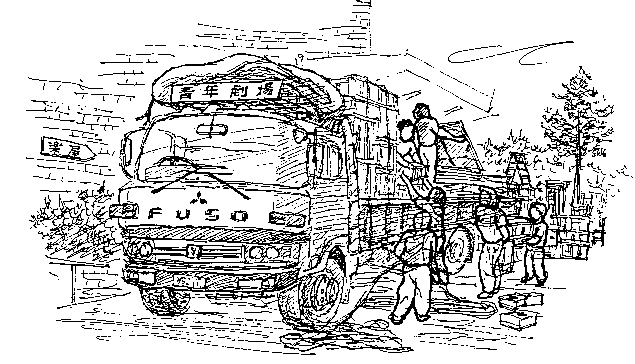
なんとしても学校公演の灯を消すわけにはいかない。焦燥に近い決意が私の中にあるが、ではそのためにまず何をすればいいのか、今のところその方策が浮かばないでいる。
(2007年5月)
※執筆者の冒頭の肩書は、当時のままになっています。
現在の肩書が分かる方は、文章末尾に表記しています。
「演劇鑑賞教室について考える」のトップページへ
青年劇場のトップページへ